 |
|||||||||||||||
■出演者
司会:星恭博さん・藪下貴子さん
ゲスト:愛知教育大学教育学博士・久野弘幸さん
私流親学:東仁王門商店街たんぽぽ会会長・小寺茂雄さん
■ 内容
 今回のテーマは、「地域活動」。地域活動への参加やボランティア活動の経験は、社会への貢献であるだけでなく、自分自身を見つめるきっかけにもなります。親子で地域活動へ参加することで、地域の人たちと交流することもできます。また、子どもたちが健やかに、そして安心して暮らせるまちづくりの推進にもつながります。
今回のテーマは、「地域活動」。地域活動への参加やボランティア活動の経験は、社会への貢献であるだけでなく、自分自身を見つめるきっかけにもなります。親子で地域活動へ参加することで、地域の人たちと交流することもできます。また、子どもたちが健やかに、そして安心して暮らせるまちづくりの推進にもつながります。最近、子どもを連れ去る事件が相次いでいます。このような状況を考えると、地域による子どもたちの安全を守る活動はますます重要になってきていると言えます。
 中村区の稲葉地学区ではあいさつ道路を設けたり、子どもたちが登校時にあいさつを交し合う運動をPTAも協力して行ったりしています。このような活動によって、子どもと地域の人たちが顔見知りになることはとても良いことです。名古屋市立中根小学校PTAでは、保護者が腕章を付けたり、自転車の前かごに「パトロール中」のプレートを付けたりして、子どもの安全を守る活動をしています。また、那古野学区では、なごのっ子を守る会が防犯教室を開いたり、「こども110番」の家を設けて、子どもたちが危ない目に合ったときに、安心して逃げ込めるようにしたりしています。
中村区の稲葉地学区ではあいさつ道路を設けたり、子どもたちが登校時にあいさつを交し合う運動をPTAも協力して行ったりしています。このような活動によって、子どもと地域の人たちが顔見知りになることはとても良いことです。名古屋市立中根小学校PTAでは、保護者が腕章を付けたり、自転車の前かごに「パトロール中」のプレートを付けたりして、子どもの安全を守る活動をしています。また、那古野学区では、なごのっ子を守る会が防犯教室を開いたり、「こども110番」の家を設けて、子どもたちが危ない目に合ったときに、安心して逃げ込めるようにしたりしています。 こうした地域での活動が行われる背景は何か。円頓寺商店街の周辺を歩いて、子どもたちを取り巻く環境の変化を調べてみると、少子化・都市化の影響で、(1)子どもが外で遊ぶことが少ない、(2)怖いおじさんがいない、(3)近所で子どもを見かけない、(4)駄菓子屋がないなど昔とは様変わりしていることがわかります。
こうした地域での活動が行われる背景は何か。円頓寺商店街の周辺を歩いて、子どもたちを取り巻く環境の変化を調べてみると、少子化・都市化の影響で、(1)子どもが外で遊ぶことが少ない、(2)怖いおじさんがいない、(3)近所で子どもを見かけない、(4)駄菓子屋がないなど昔とは様変わりしていることがわかります。 今回のゲストは、愛知教育大学・教育学博士の久野弘幸先生。地域の教育力が低下した原因は、少子化によって交流の機会がなくなったから。そして、子どもたちの生活に「三間」がないから。「三間」とは、時間、空間、仲間。今の子どもたちは忙しくて時間がない。都市化の進行で空間がない。少子化の影響で仲間がいない。また、最近の家族は車で移動するカプセル生活。こうした孤立した生活習慣が家族と地域を遮断する。大事なのはまずは顔見知りの関係を作ること。
今回のゲストは、愛知教育大学・教育学博士の久野弘幸先生。地域の教育力が低下した原因は、少子化によって交流の機会がなくなったから。そして、子どもたちの生活に「三間」がないから。「三間」とは、時間、空間、仲間。今の子どもたちは忙しくて時間がない。都市化の進行で空間がない。少子化の影響で仲間がいない。また、最近の家族は車で移動するカプセル生活。こうした孤立した生活習慣が家族と地域を遮断する。大事なのはまずは顔見知りの関係を作ること。 名古屋市立赤星小学校PTAのスポーツクラブを訪ねました。この活動を始めてから、公園で遊ぶ子どもが増えたそうです。PTA会長さんにインタビューすると、子どもに接するのが怖い、子どもに気を使うという親にはなってほしくない。子どもに心を配りたいとのこと。
名古屋市立赤星小学校PTAのスポーツクラブを訪ねました。この活動を始めてから、公園で遊ぶ子どもが増えたそうです。PTA会長さんにインタビューすると、子どもに接するのが怖い、子どもに気を使うという親にはなってほしくない。子どもに心を配りたいとのこと。最後に、久野先生から、子どもと自然に関わる場所をつくること、そして、自分のできることから、ほんの少しの努力と工夫で始めることが大事というアドバイスをいただきました。
私流親学は、東仁王門商店街たんぽぽ会会長・小寺茂雄さん。
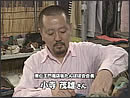 今の若者は、話し掛けないとなかなか喋らない。あいさつができる、話ができる子どもになってほしいというメッセージをいただきました。
今の若者は、話し掛けないとなかなか喋らない。あいさつができる、話ができる子どもになってほしいというメッセージをいただきました。親学川柳は、「自立へと 目は離さずに 手を放す」(緑区・山口登美子さん)。子どもの成長のために子どもに任せることは良いことです。でも、手を放したからこそ、よりしっかり見守っていくことが大切だと思います。
▲ このページのトップへ
|家庭教育テレビ番組|幼稚園の子どもたち|親度チェック|子育て相談機関窓口|